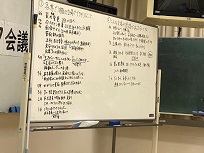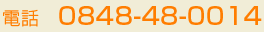HOME
�b��搶�i���@���j�u���O�b���Â̗����b�@���ē��b�f�Èē��b�\�h�����b�R�c�r�b��q�����b�z���C�g�j���O�b�C���v�����g�b�X�|�[�c�}�E�X�K�[�h
���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��
���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��



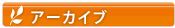

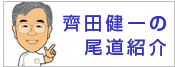

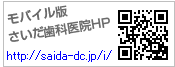

 �@�@�@
�@�@�@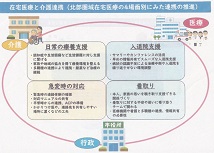
 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@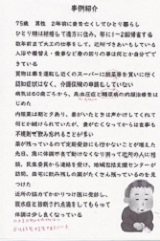 �@�@�@
�@�@�@